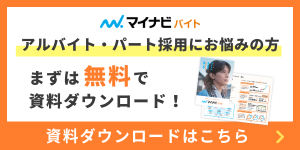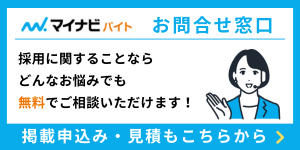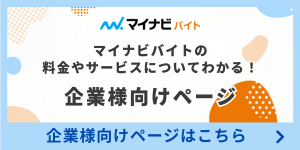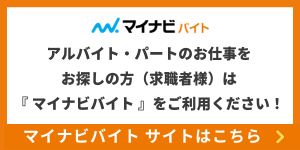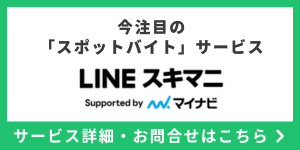「求人用の写真をどのように撮影すれば良いか分からない」「本格的なカメラを使ったことがないため不安だ」と感じる採用担当者も少なくないはずです。しかし、実は特別なカメラや技術がなくても、ちょっとしたコツを知っておけば、応募者の目を引く写真を撮ることができるようになります。
「求人用の写真をどのように撮影すれば良いか分からない」「本格的なカメラを使ったことがないため不安だ」と感じる採用担当者も少なくないはずです。しかし、実は特別なカメラや技術がなくても、ちょっとしたコツを知っておけば、応募者の目を引く写真を撮ることができるようになります。
求人写真は、言葉以上に「職場の雰囲気」や「スタッフの魅力」を伝えてくれる重要な要素です。実際、ハローワークでも「作業風景や職場環境を画像で説明することで、文字情報だけでは伝えきれない魅力を伝えられる」と推奨されています *1。視覚情報は求人内容を補完し、応募率の向上にもつながるのです。
今回は、カメラ初心者でも今すぐ実践できる撮影テクニックをご紹介します。求人写真撮影を検討している採用担当者の方は、ぜひチェックしてください。
*1 引用)石川県労働局「Road to 魅力ある求人」(企業の魅力を伝えるための画像活用)
目次
※各目次をクリックすると、読みたい内容をすぐにご覧いただけます。
撮影は事前予告が成功の鍵
当日の急な依頼は避けましょう
「今日、急きょ写真を撮らせてもらえませんか?」という依頼は、撮影される側のスタッフにとって予期せぬ負担となります。事前に身なりや雰囲気を整えてもらった方が魅力を伝えやすい写真につながります。撮影の1週間前にはスケジュールを共有しておきましょう。
事前告知のメリット:
・心の準備:写真撮影に対する緊張感を軽減させられます。
・メイクの準備:普段ノーメイクの方も撮影用に準備が必要です。
・髪型のセット:ヘアスタイルを調整してもらえば、清潔感を伝えることができます。
・服装の準備:制服のクリーニングをする時間が取れます。私服で撮影する場合は、採用担当者が想定する服装とのギャップを防ぐことができます。
理想的な事前連絡のタイミング:
①1~2週間前:撮影日を通知し、スタッフに心の準備を促します。
②3~4日前:準備する物や当日の流れなど、詳細を案内します。
③前日:関係者へのリマインドと、当日のスケジュール確認を行います。
事前連絡で伝えるべき内容
撮影に協力してくれるスタッフが安心して撮影に臨めるよう、依頼する際は具体的な情報を提供しましょう。
スタッフが安心できる案内テンプレート
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【撮影のお知らせ】
日時:○月○日(○)○時〜○時(約1時間)
目的:求人広告用写真の撮影撮影内容:
・スタッフ集合写真
・業務風景、個別作業シーン準備のお願い:
・日常通りのメイク・服装で差し支えありません
・制服は清潔なものを着用してください
・アクセサリーやネイルは普段通りでOKです
・体調管理にもご注意くださいその他:
・写真は求人サイト○○に掲載予定です
・撮影に不安がある方は、事前にご相談ください
・ご不明点はいつでもお問い合わせください
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
このように「何の写真を、いつ、どんな目的で、どのように撮影する予定なのか」が事前に明示されていると、スタッフもよりリラックスして撮影に臨めます。
まずはスマホでOK!機材選びの心配は不要
スマートフォンが普及した現在、多くの採用担当者が「一眼レフのような本格的なカメラを用意するのはハードルが高い」と感じているかもしれません。しかし、実はある程度のクオリティの写真であれば、スマートフォンでも十分。手軽さと撮影性能により、魅力的な求人写真を撮影することが可能です。
なお、求職者が求人広告にどのような要素を求めているか考えて撮影することも重要です。最近の求職者は「一緒に働く人」「仕事内容」「職場の雰囲気」が分かる写真を欲しており、かしこまったものより日常の様子が伝わる“リアリティ”ある写真に価値を感じる人が多いようです。求人写真は単なる“装飾”ではなく、求職者の関心を引く有力な情報として機能することが期待できます。
つまり、特別な機材がない場合でも、スマートフォンを使ってリアルな職場の雰囲気や働くスタッフの表情をしっかり伝えられれば問題ないのです。
基本のスマホ撮影テクニック
スマートフォンでの撮影をより効果的に行うために、以下の基本テクニックを押さえておきましょう。
・光の意識:
被写体への光の当たり方は、正面から当たる順光、背景からの逆光、横からのサイド光があります。順光は顔がはっきりとした印象、サイド光はコントラストによる立体感のある印象、逆光は柔らかい光で包んだ優しい印象になります。

 ・構図の工夫:
・構図の工夫:
スマートフォンのグリッド線(3分割ライン)を活用することで、バランスの良い構図が簡単に作れます。被写体を中央から少しずらすだけで余白が生まれ、オシャレな雰囲気を醸し出すことができます。
・手ブレ防止:
三脚や安定した台を使うのがベストですが、難しい場合は両手でスマートフォンをしっかり持ち、脇を締めて撮影すれば、ブレが大きく改善します。
スマートフォンは直感的に構図やタイミングを捉えやすい点も利点です。まずはこれらを押さえて、自然な職場の様子を捉えてみましょう。
その他の便利なスマホ機能も活用しよう
さらに一歩進んだ撮影に挑戦したい方は、以下の機能を使用することもおすすめです。
・露出調整:
iPhoneでは、撮りたい被写体をタップした後に現れる「太陽アイコン」で明るさを調整できます。Androidでも、同様に明るさ調整(EV補正)機能が使えます。*2
・望遠カメラの活用:
スマートフォンに望遠(2~5倍)カメラが搭載されている場合、広角(一般のメインカメラ)よりも歪みが少なく被写体を自然に写すことが可能です。人物のポートレート撮影に向いています。*3
*2 参考)関西電力・おとなも学べる!教えて!かんでん「スマートフォンでいい感じの写真を撮る必勝法」
*3 参考)カメラのキタムラ「スマホで簡単!綺麗にブツ撮りをするコツを解説」
集合写真は“想像以上に近づく”ことがポイント
距離感の目安を覚えよう
集合写真を撮る際、「遠すぎて人物が小さくなる」「間延びした印象になる」と感じたことはありませんか?実は、被写体に思い切って近づくことが、画面にボリュームと温かみを生む秘訣です。
ただ、被写体を画面いっぱいになるよう撮影すると、掲載サイズや比率の関係で端が切れる可能性があります。また、レンズの特性上、スマホのカメラは特に端にいくにつれ歪みが出てしまいます。
そのため、撮影時は上下左右に少し余白を残した状態にしておき、使用比率に合わせて後から中央部分をトリミング(切り取り)するのがベストです。
距離の目安としては、お互いの肩同士が軽く触れ合う程度が理想。「ちょっと近すぎるかな?」と思うくらいがちょうど良いです。5人以上の場合は、前後2列に分かれて撮影しましょう。
明るさ調整は「窓際」が最強の味方
求人写真では、自然光を最大限に生かすことがとても効果的です。時間帯としては、明るい日中がベスト。なるべく夕方や早朝の暗い時間は避けましょう。自然光を生かすためにも、窓際の明るい場所で撮影することをお勧めします。
シチュエーションが確定したら、スマートフォンの機能を活用しましょう。画面をタップして明るさを調整し、HDR機能(白飛びや黒つぶれを防ぎ、自然で鮮明な1枚の写真を作成する機能)をONにするのがおすすめ。不自然な影が出やすいため、フラッシュは基本的にOFFに設定しましょう。
構図は「3つのエリア」を意識するだけ
視線を誘導し、バランスの良い写真を撮るには構図も大切です。特に、求人サイトでは、写真に店名や募集要項が重なる場合や、文字入れ加工をする場合も多くあります。そのため、写真の上部20%は「文字エリア」として事前に空けておくと後々便利です。以下のステップを踏まえて、正しい構図を見つけましょう。
1. 画面を上・中・下の3つに分ける
2. 人物は「中」の部分に配置する
3. 「上」または「下」のスペースに文字を入れる場合は、それも考慮して余白を作る
また、構図について、次の要素も踏まえると、より美しい写真を撮影できます。
・三分割法:
画面を縦・横それぞれ3分割し、9つの枠を作ります。その枠の交点や線に沿って被写体を配置すると、自然で安定感のある構図になります。
・水平・垂直を意識:
建物やラインの傾きは写真の印象に影響しやすいです。グリッド機能や三脚を使って、まっすぐになるよう安定させましょう。
・余白の活用:
「人物が窮屈に見える」「構図が固い」と感じたら、後ろの壁との間に少し余裕を持たせると奥行きが生まれます。
撮影リストを作って撮り忘れ防止
何を撮るべきか事前の把握を
撮影当日、「何を撮れば良いのか分からない」と迷う時間が多いと効率を下げてしまいます。事前に撮影リストを作成しておくことで、どのようなイメージを撮りたいかスタッフとも共有しやすいため、スムーズに撮影を進められます。
基本の撮影リスト:
人物写真
・スタッフ全員の集合写真
・小グループ写真(2~3人)
・個人の作業風景
・笑顔のアップ写真
・カメラから目線を外した、スタッフ同士の談笑シーン
※個人情報を保護するため、名札を付けている場合は外した上で撮影しましょう仕事内容が分かる写真
・接客、調理、事務などの実務シーン
・使用道具や機器
・完成した商品やサービス職場環境が伝わる写真
・店舗やオフィス全体
・休憩室やロッカー
・制服やエプロン
撮影順や時間配分も計画しておく
撮影リストを作るだけでなく、撮影の順番や時間配分も事前に決めておきましょう。自然な流れとしては「人物写真」→「仕事内容」→「職場環境」で、各カットの目安時間も決めておくと、スタッフも安心して撮影に臨むことができます。大まかなタイムスケジュールの目安は後述します。
身だしなみチェックは撮影前の5分間で実施
求人写真は、応募者にとって「働く職場がどんな雰囲気か」を知る重要な手がかりです。特に髪型や服装、アクセサリーなどは、職場でのルールや自由度をイメージする材料になります。
年齢や性別、役職などさまざまなスタッフをバランスよく撮影することで、多様性をアピールできます。これにより、応募者が「自分も働けそう」と安心できる効果が期待できます。多様性を示すには、年齢や髪型の異なるスタッフをバランス良く撮影することが効果的です。
撮影前の身だしなみチェックリスト:
髪色・髪型:長髪の場合の結び方、前髪の長さや色のトーン
アクセサリー:ピアス、ネックレス、時計などの許容範囲
ネイル:長さや色の基準
服装:制服の着用や私服での撮影可否
肖像権の同意は「撮影前」に必ず取る
採用写真を公開する場合、肖像権や個人情報に関する配慮は必ず行いましょう。無断で使用すると法的トラブルにつながる可能性があるため、事前に確認しておくことが重要です。
手順の例:
1. 事前連絡時に概要を説明
「求人広告に使用します」
「掲載媒体は〇〇サイトです」
「使用に同意できない場合は遠慮なくお知らせください」2. 撮影当日の最終確認
「写真撮影について問題ないですか?」
「求人サイトに掲載してもよろしいですか?」3. 退職後の取り扱いの確認
「退職後も写真使用を継続して良いか」
「使用停止希望の場合の連絡方法」
これらの手順を踏むことで、トラブル防止とスタッフへの配慮を両立できます。
失敗しない撮影の進め方
前述した通り、撮影当日は時間が限られているため、事前のタイムスケジュール作成が必須です。短時間で集中して撮影することで、スタッフの負担を減らし、自然な表情を引き出せます。
例)1時間の撮影スケジュールイメージ
0~7分:機材チェック、撮影場所確認
7~10分:スタッフへの説明・同意確認
10~13分:身だしなみチェック
13~23分:集合写真(全員→小グループ→個人)
23~43分:業務写真(接客・作業風景)
43~53分:職場環境の写真(店内・オフィス・休憩室)
53~60分:写真確認・スタッフへのフィードバック
実際の撮影では、「いいですね!」「素敵な笑顔です!」などポジティブな声かけが自然な表情を引き出します。スタッフが緊張している場合は、軽く雑談を交えてリラックスしてもらいましょう。なお、その場でどの写真がベストかを選ぶよりも、同じ構図で5~10枚撮影し、表情の良いものを後で選ぶ方法が効率的です。
また、撮影時には次のポイント踏まえて対応しましょう。
・表情:笑顔はもちろん、業務中の真剣な表情もバリエーションとして撮影
・姿勢:背筋を伸ばす、肩の力を抜く
・小物や背景:周囲に余計な物や機密情報などが映り込まないよう確認。当日までにある程度準備しておくのがベスト
撮影当日の心配りポイント
スタッフが緊張せずに撮影に臨めるよう、細やかな配慮を心がけましょう。例えば、その場で写真を見てもらい、どのような見え方になるのか共有すれば安心感につながります。撮影中も積極的に声をかけ、緊張をほぐすことも大切です。また、スタッフから「もう一度撮りたい」と希望があれば、柔軟に対応しましょう。
まとめ:準備8割、撮影2割で成功する
求人写真の仕上がりは、当日の撮影そのものよりも事前準備によって大きく左右されます。初心者でも、次の3点を意識するだけで印象的な写真を撮影可能です。
1. 事前連絡でスタッフの準備時間を確保
撮影予定は少なくとも1週間前に連絡するのがおすすめ。準備内容(髪型・服装・アクセサリー等)を詳細に伝えましょう。
2. 自然光を活用し、集合写真は思った以上に近づく
窓際での撮影が最も簡単です。人物同士の距離は、肩と肩が軽く触れる程度の近さを目安にしてください。複数人の撮影の際は前後列に分けるなど、人数に応じた調整をしましょう。
3. 複数枚撮影し、後で良いものを選ぶ
同じ構図で5~10枚程度撮影しましょう。後から表情や姿勢を比較して、最も自然で魅力的な1枚を選ぶことができます。
また、撮影をスムーズに行うために、事前準備は以下の項目を確認しておきましょう。
事前準備のチェックリスト:
・撮影日程の1週間前予告
・撮影内容と準備事項の説明
・撮影リスト作成(人物・業務・職場環境)
・身だしなみチェック項目の整理
・肖像権使用の同意確認
・当日のタイムスケジュール作成
・機材・スマートフォン・三脚の準備
「カメラのプロではないけれど、スタッフの魅力は誰よりも知っている」という強みを生かし、事前準備と心配りで良い写真を撮影できることが、求職者に職場の魅力を伝える最大のポイントです。
最初は不安でも、回数を重ねることで撮影のコツを習得できます。今回紹介した内容を踏まえて、求職者に魅力が伝わる求人写真を撮影してくださいね。
監修者プロフィール

株式会社 frame plus代表取締役/ディレクター 松井大樹
あらゆるジャンルの企業のWEBサイトやカタログのほか、雑誌、CMなど、さまざまな媒体において、写真、動画、ドローンの撮影サービスを提供する、“写真と動画”のプロフェッショナル集団『株式会社frame plus』代表取締役。人物や建築、料理、商品などをメインに撮影しており、年間撮影件数は企業のみで300件以上に上る。
https://frameplus.jp/