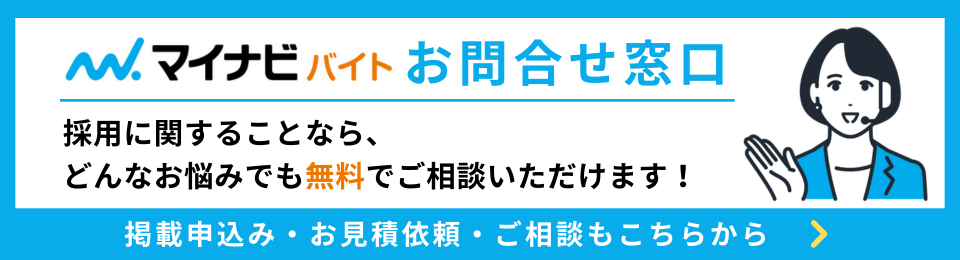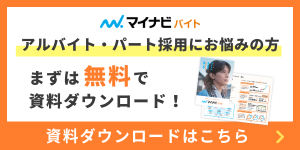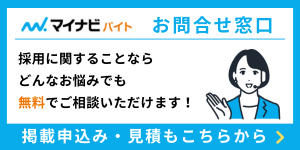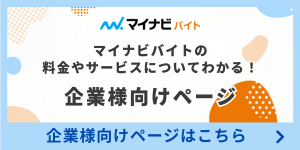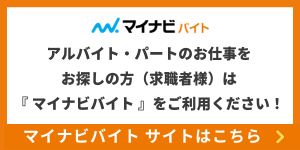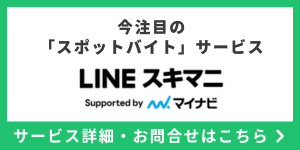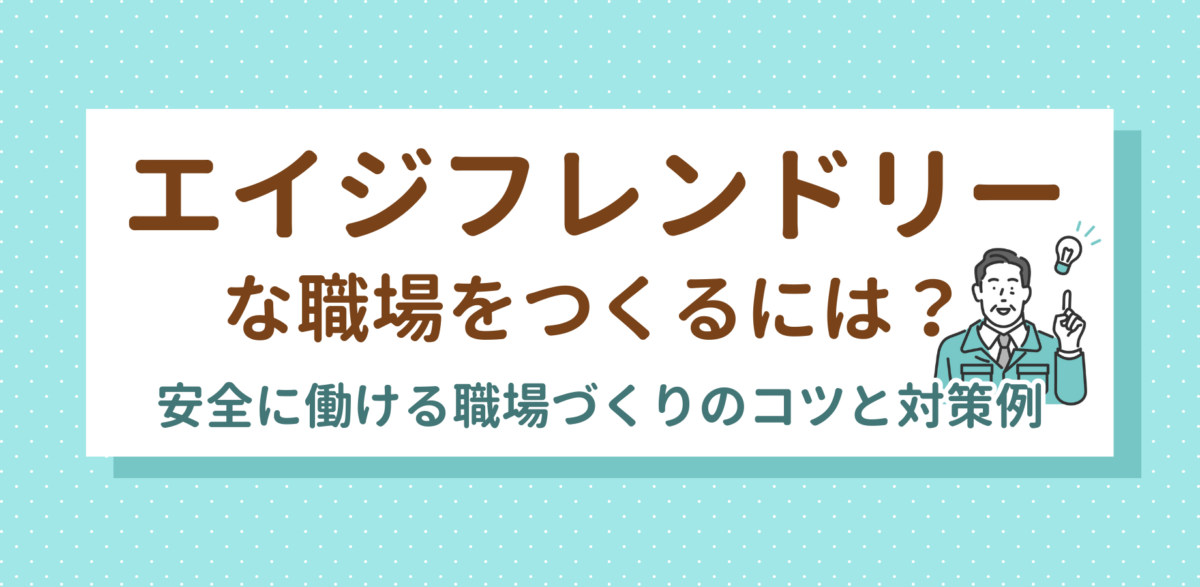
近年、高年齢者の社会進出が進み、過去10年間で60歳以上の労働者数は約1.5倍まで増加しました。同時に、高齢者の労働災害の報告数も年々増加しています。
そのため、高年齢者の特性に配慮した「エイジフレンドリーな職場」のニーズが高まっています。これは高年齢者だけではなく、同じ職場で働く全てのスタッフの安全にもつながり、さらに定着率向上や人手不足の解消などのメリットも期待できます。
そこで今回は、厚生労働省が2020年に策定した「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」に基づき、アルバイト雇用者が押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。また本記事では、60歳以上で現在就業している人を「高年齢労働者」と呼びます。
目次
※各目次をクリックすると、読みたい内容をすぐにご覧いただけます。
「エイジフレンドリーガイドライン」の内容を徹底解説!
1.安全衛生管理体制の確立
2.職場環境の改善
3.高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
4.高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応
5.安全衛生教育
まとめ
「エイジフレンドリーガイドライン」の内容を徹底解説!
1.安全衛生管理体制の確立
安全衛生管理体制とは、働く人の安全と健康を守るために、労働災害の防止に向けた取り組みを行う企業側の体制のことです。
1-1.経営者が労災対策の方針を明らかにする
まず、企業経営者は高年齢労働者が働きやすい環境を整えるために、どのような取り組みを行うのかを社員に伝える必要があります。さらに取り組みを具体化させるために、専任メンバーの選出や、高年齢労働者にヒアリングすることも重要です。
ここで気を付けるべきポイントは、高年齢労働者が体調や仕事のことで不安にならないように配慮することです。一人で悩みを抱え込まないように、相談窓口の設置やスタッフ同士の声かけなど、風通しの良い職場環境を整えることも効果的でしょう。
1-2.労災リスクを洗い出し、対策に優先順位をつける
次に、身体機能の衰えによる労災リスクを確認し、原因と対策を考えます。リスクの洗い出しには、高年齢労働者に「事故になりそうだった時(ヒヤリハット)」の聞き取り調査を行うことや、厚生労働省が提供している「エイジアクション100」のチェックリストを活用することが有効です。
参考)厚生労働省「エイジアクション100」
2.職場環境の改善
高年齢労働者に多い労災事故は「転倒」「墜落」「転落」の3つです。これらを防ぐためには、衰えた身体機能をサポートする設備や装置の導入、作業環境の改善が欠かせません。厚生労働省が策定した「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」によると、以下のような安全対策を行うことで労災リスクを抑えることができます。
転倒防止
・床や通路の滑りやすい箇所に防滑素材(床材や階段用シート)を採用する。
・防滑靴を利用させる
・階段には手すりを設け、可能な限り通路の段差を解消する
・解消できない危険箇所に標識等で注意喚起
・水分・油分を放置せず、こまめに清掃する
熱中症対策
・熱中症の初期症状を把握できるウェアラブルデバイス等のIoT機器を利用する
・涼しい休憩場所を整備し、通気性の良い服装を準備する
身体的な負担軽減
・パワーアシストスーツ等を導入する
・リフト、スライディングシート等を導入し、抱え上げ作業を抑制
・不自然な作業姿勢をなくすよう作業台の高さや作業対象物の配置を改善する
視力のサポート
・通路を含め作業場所の照度を確保する
・パソコンを用いた情報機器作業では、照明、文字サイズの調整、必要な眼鏡の使用等により作業姿勢を確保する
聴覚のサポート
・警報音等は聞き取りやすい中低音域の音、パトライト等は有効視野を考慮 など
引用)
厚生労働省「エイジフレンドリーガイドライン」
厚生労働省「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」
3. 高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
労災を防ぐためには企業と高年齢労働者それぞれの取り組みが欠かせません。企業側は高年齢労働者の健康状態と体力の度合いを把握し、適切な措置を講じる必要があります。また、労働者に対して「睡眠時間」「飲酒」「服薬状況」など、自身の体調管理ができるように働きかける必要があります。
3-1.健康診断は必ず受診させるように
まず、定期的に健康診断を実施することが重要です。たとえ、労働安全衛生法で対象外の従業員がいたとしても、健康診断の受診を促すことや、受診のための勤務時間の変更、休暇の取得などの柔軟な対応が必要でしょう。
3-2.「体力チェック」は高年齢労働者の体力を数値化できる
加えて、筋力の衰えを確認する「体力チェック(フレイルチェック)」や厚生労働省が作成した「転倒等リスク評価セルフチェック票」なども併せて実施します。これらは高年齢労働者の体力を数値化できるため、安全対策に活かしやすいというメリットがあります。ただし、測定方法と評価基準については、安全衛生委員会などの審議を踏まえた上で、合理的な水準にする必要があります。
4.高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応
4-1.体力にあった仕事や働き方ができるように配慮する
企業は高年齢労働者の職務内容や働き方を、各々の健康状態や体力に合わせた内容に変える必要があります。
たとえば、年齢を重ねるほど脳や心臓疾患のリスクが高まるため、病気を治療している労働者に対しては、労働時間の短縮や夜間シフトの削減などの対応策が考えられます。また、基礎疾患を抱えている方には、体力的な負担が軽い仕事への配置換えや、ワークシェアリングによる作業分担なども検討されるべきです。
4-2.必ず高齢者本人の了解を得ること
ここで気を付けるべきポイントは、健康状態や体力は個人差が大きいということです。そのため、上記のような安全措置を取る際には、労働者それぞれの状況を正しく把握し、本人の了解を得る必要があります。
4-3.メンタルヘルスも含めた健康サポートが必要
また、健康増進に向けた取り組みも欠かせません。日常的な体力づくりやトレーニングに加え、メンタルヘルスのケアなど、企業は高年齢労働者が心身ともに健やかな状態で働けるようにサポートする必要があります。具体的な取り組みを決める際には、厚労省による以下の指針を参考にしてください。
・事業場における労働者の健康保持増進のための指針
・労働者の心の健康の保持増進のための指針
5. 安全衛生教育
5-1.高年齢労働者には写真や図なども使って説明
安全な職場づくりを進めるためには、労働者と管理者のどちらにも安全衛生教育を行う必要があります。
まず、高年齢労働者に対しては、作業手順や体力維持の重要性についてわかりやすく説明します。その際、文字だけの資料ではなく、写真や図、映像などを使用することで、より理解を深めることができます。また、集合研修ができない職場では視聴覚教材(メディア教材)を利用する方法も考えられます。
5-2.未経験者にはより丁寧に指導する
高年齢労働者の中には、再雇用や再就職で経験の無い仕事に就く場合もあります。事故防止だけではなく、スムーズに仕事が進められるように、未経験者には時間をかけて丁寧に指導をするように心掛けてください。
5-3.管理職にも労災対策の教育をおこなう
サービス業など、一見危険そうに思えない職場にも労災リスクが潜んでいます。そのため、管理職側にも高年齢労働者の特徴や安全対策について教育し、管理体制を強化することも大切です。
まとめ
エイジフレンドリーな職場を実現するためには、企業が労災リスクを理解し、それに対する対応策を講じることが重要です。また、労働者自身も健康づくりの重要性を理解し、日ごろから体調管理に気をつける必要があります。
高年齢労働者が働きやすい職場づくりは、一見、高齢者だけにメリットがあるように思えるかもしれません。しかし、労災リスクを洗い出して対策することは、他のスタッフの安全にもつながり、長期的には企業の生産性向上にも寄与します。
少子高齢化が進む今、高齢者の存在はますます重要になっています。アルバイト雇用者は、この厚生労働省の「エイジフレンドリーガイドライン」を参考に、職場環境を整えると良いでしょう。
マイナビバイト掲載のご依頼や採用に関するお悩み、お気軽にご連絡ください!
「マイナビバイトの掲載料金が知りたい」「掲載の流れを知りたい」とお考えの採用担当者様は、ぜひ以下よりお問い合わせください。
マイナビバイトでは、求人掲載をお考えの方だけでなく、アルバイト・パート採用に関するお悩みをお持ちの方からのご相談も歓迎しております。私たちは、応募から採用・定着までをしっかり伴走し、貴社の課題解決に寄り添います。
マイナビバイトに問い合わせる(無料)
電話番号:0120-887-515(受付時間 9:30~18:00)
さらに、料金表・サービスの概要・掲載プラン・機能紹介などを詳しくまとめたサービス資料もご用意しています。
「まずは資料を見てみたい」という方は、下記リンクから無料でダウンロードいただけます。
マイナビバイトは、貴社の採用活動を全力でサポートいたします。ぜひこの機会にお問い合わせください。