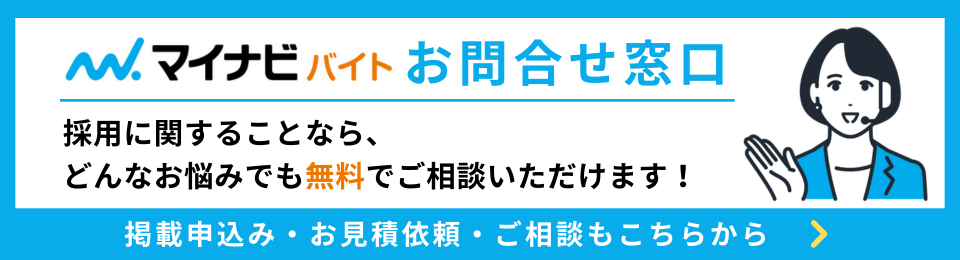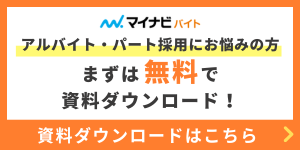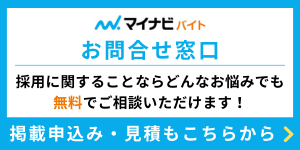従業員を採用する際に必要となる「雇用契約書」とは、雇用主と労働者との間で結ばれる、契約に関する重要な文書のことです。ただ、「雇用契約書」を書面で残しておくことは法律で明確に義務付けられているわけではありません。
また、類似するものとして交付義務のある「労働条件通知書」がありますが、それぞれの書面が持つ意味はどう違うか、書面に関しての重要性などを解説いたします。
目次
※各目次をクリックすると、読みたい内容をすぐにご覧いただけます。
「雇用契約書」と「労働条件通知書」の大きな違い
「雇用契約書」の役割
「労働条件通知書」の役割
法律上の作成義務とその重要性
1.労働条件通知書の作成義務
2.雇用契約書の重要性
雇用契約書を作成する際の注意点
1. 必要な記載事項を網羅する
2.労働時間制を明示する
3.転勤や人事異動の可能性を示す
4. 試用期間を明記する
2024年4月から記載必須に変更された項目
1.新たに必須となる記載項目
2.変更の背景と目的
マイナビバイト掲載のご依頼や採用に関するお悩み、お気軽にご連絡ください!
そもそも「雇用契約書」とは?
雇用契約書とは、雇用主と労働者が結ぶ契約の内容をまとめた書類で、以下のような重要な情報が含まれています。
・給与(賃金):労働者が受け取る賃金 、支給される日など
・勤務期間:いつからいつまで働くのか
・勤務場所:どこで働くのか
・労働時間:1日に働く時間や週の勤務日数
・業務内容:どのような仕事をするのか
・昇給:給与が上がる条件やタイミング
・退職:仕事を辞める際のルール
雇用主と労働者が合意の上で契約書に署名することで正式に契約が成立し、労働者の権利を守るために重要な書類となります。また、書面での合意があることでトラブルを未然に防ぐこともできます。契約書には法的な効力があるため、雇用主にとってもリスク管理の手段として欠かせないものなのです。
「雇用契約書」と「労働条件通知書」の大きな違い
「雇用契約書」と「労働条件通知書」は、どちらも雇用に関する重要な書類となります。それぞれの違いを少し整理していきましょう。
「雇用契約書」の役割
・役割:労働者と雇用主の双方が合意した内容を記載した書類です。
・署名:労働者と雇用主の双方が署名する必要があります。
・内容:給与、勤務時間、業務内容などの具体的な契約条件が含まれます。
「労働条件通知書」の役割
・役割:雇用契約を結ぶ際に、雇用主が労働者に通知する義務のある事項を明示した書類です。
・署名:雇用主が一方的に作成する書類のため、 労働者の署名は必要ありません。
・法律上の義務*1:労働基準法第15条に基づき、雇用主には作成が義務付けられています。
このように「雇用契約書」は、労働者と雇用主の合意を示すための書類で、「労働条件通知書」は、雇用主が法律に従って労働者に必要な情報を伝えるための書類です。それぞれ異なる役割を果たしていますが、どちらも雇用主と労働者の信頼関係の構築には欠かせない要素となります。両方を適切に作成することが、労働環境の向上と法令遵守のために非常に重要ですので、混同しないように双方の役割と重要性を理解することが大切です。
*1 参考)労働基準法第 15条第 1項 「労働基準法の基礎知識」
法律上の作成義務とその重要性
上記の通り、「雇用契約書」には法律上の作成義務はありませんが、作成することは推奨されています。ただ「労働条件通知書」には、労働基準法第15条により、雇用主は労働者に対して、賃金や労働時間などの条件を明示する必要があるため作成義務があります。ここでは、書面の重要性について詳しくご説明します。
1.労働条件通知書の作成義務
労働基準法第15条により、雇用主は労働者に対して賃金、労働時間、休暇、業務内容などの労働条件を明示することが義務付けられています。また、労働者が自分の働く条件を理解し、納得した上で働くための情報を提供する事が目的です。
2.雇用契約書の重要性
【法的な効力】
雇用契約書は、労働者と雇用主が合意した内容を記載した書類であり、双方の署名があることで法的効力を持ちます。これにより契約内容が明確になり、後々のトラブルを避けることができます。
【トラブル防止】
口頭での契約は、誤解や記憶の違いからトラブルの原因になる恐れがあります。書面で契約を結ぶことで雇用主と労働者の間でルールが明確になり、双方が同じ理解を持つことができます。
【リスク管理】
雇用契約書を作成することで、雇用主と労働者の関係を明確にし、法的なリスクを軽減することができます。例えば、労働者が契約内容に不満を持った場合でも、契約書があればどのような条件で勤務をすることになっているのか確認できます。
「労働条件通知書」は法律上の義務として雇用主が作成しなければならない書類ですが、「雇用契約書」は作成義務がありません。しかし作成することは、雇用主と労働者の間で信頼関係を築き、トラブルを防ぐためにも重要です。書面での合意があることで、雇用主側はリスクを管理しやすくなり、労働者側は安心して働くことができるため、雇用契約書の作成は労使双方にとって大切なステップとなります。
雇用契約書を作成する際の注意点
雇用契約書を作成する際には、以下のポイントをしっかりと押さえることで、円滑な雇用関係を築くことができます。
1. 必要な記載事項を網羅する
<絶対的記載事項>
書面に必ず記載しなければならない内容です。具体的には以下のような項目があります。
・賃金:基本給、手当、賞与、交通費など具体的な給与額や支払い方法(銀行振込、現金など)、支払い日(毎月何日など)を明記します。
・労働時間:始業・終業時刻、休憩時間、週の労働日数などを具体的に記載します。
・休日・休暇:週休の有無、年次有給休暇の取得条件、特別休暇の有無などを明記します。
・業務内容:労働者が行う具体的な業務や役割を明記します。
<相対的記載事項>
業種や運営指針 により異なりますが、必要に応じて記載する内容です。
例えば、福利厚生(健康保険、年金、交通費支給など)、昇給や昇進の条件などが含まれます。
2.労働時間制を明示する
・労働時間制の種類:変形労働時間制やフレックスタイム制など、適用する労働時間制を明記します。これにより、労働者がどのような働き方をするのかを理解しやすくなります。
・具体的な労働時間:具体的な始業・終業時刻や、休憩時間も明記することが重要です。
例)始業は9時、終業は17時、休憩は12時~13時まで など
3.転勤や人事異動の可能性を示す
・転勤の可能性:労働者が職種や条件を変更する可能性がある場合、その旨を明記しておくことが重要です。これにより、労働者は将来の働き方についての理解を深めることができます。
・具体的な条件:転勤や異動の範囲(国内外など)についても記載しておくと良いでしょう。例えば、「転勤は国内の支店に限る」といった具体的な内容が望ましいです。
4. 試用期間を明記する
・試用期間の設定:試用期間を設ける場合、その期間や条件を具体的に明記します。
例)3ヶ月の試用期間中は、基本給の80%とする など
・本採用の条件:条件や評価基準も記載しておくと、労働者にとって安心材料となります。例)試用期間終了後は、業務評価に基づき本採用の可否を決定する など
上記を踏まえて雇用契約書を作成することで、労働者と雇用主の間のルールを明確にすることができます。また、労働者が安心して働ける環境を提供するため、労働者と雇用主の信頼関係を築くためにも、契約書の内容は非常に重要なツールですので、丁寧に作成することを心がけましょう。
2024年4月から記載必須に変更された項目
労働者の権利をより一層保護するために、2024年4月から雇用契約書に記載必須となる項目が変更されました。賃金や労働時間に関する詳細な情報提供が求められるため、雇用主は最新の法令に基づいた内容を確認し、適切に雇用契約書を作成することが重要です。以下に、変更点とその重要性について説明します。
1.新たに必須となる記載項目*2
・就業場所と業務変更の範囲
労働契約の締結や有期労働契約の更新の際には、就業場所や業務内容に加えて「変更の範囲」も明示する必要があります。
・更新上限の有無と内容
有期労働契約の締結や契約更新の際には、契約の更新に上限がある場合はその有無と具体的な内容を明示する必要があります。
・無期転換申込機会
「無期転換申込権」が発生する際には、その更新タイミングごとに無期転換を申し込むことができる旨を明記する必要があります。
・無期転換後の労働条件
「無期転換申込権」が発生する際には、その更新タイミングごとに無期転換後の労働条件について明示する必要があります。
*2 引用)厚生労働省 「2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました」
2.変更の背景と目的
・労働者の権利保護:労働者が自身の労働条件を正確に理解し、納得した上で働くことを促進するために行われています。また、公正で安定的な雇用関係を構築するため、以下の基準が改正されました。
・有期雇用契約の締結や更新:更新上限を新たに設ける場合や短縮する場合は、労働者にあらかじめ説明しなければなりません。
・雇止めの予告や理由の明示:契約を更新しない場合は、契約期間満了日の30日前までに予告をし、労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は交付しなければなりません。
・法令遵守の強化:雇用主は新たな法令に基づいた内容を再確認した上で、適切に契約書を作成することが求められます。これにより、法令遵守を確保して信頼性を高めることができます。
・労使間の信頼関係の構築:明確な契約内容は、雇用主と労働者の間の信頼関係を築くための基盤となります。労働者が自分の労働条件を理解し、納得できることで、職場の満足度や生産性が向上することが期待されます。
2024年4月からの雇用契約書に関する変更は、労働者の権利を保護し、雇用主の法令遵守を促進するためにとても重要な書面です。採用担当者は、新たな基準に基づいて契約書を作成し、労働者との信頼関係を築くことが求められます。これにより、労働環境の改善や事業の持続可能な成長につながるでしょう。
まとめ
「雇用契約書」は、雇用主と労働者の間で結ばれる法的な合意書であり、賃金や業務内容、労働条件や賃金、労働時間などの重要な情報を明示するものです。対して「労働条件通知書」は、労働条件を通知するものであり、必ずしも契約としての効力を持つわけではありませんので大きな違いの1つと言えるでしょう。
法律上、雇用契約書の作成は義務付けられておりませんが、適切な契約書を作成することで、トラブルを未然に防ぐことができます。総じて、雇用契約書は労働者と雇用主の間の信頼関係を築くための重要なツールであり、法令遵守と労働環境の改善に寄与するものです。
採用担当者は、これらのポイントを理解し、適切な雇用契約書を作成することが必要不可欠となります。
<監修者プロフィール>
社会保険労務士法人 最首総合事務所 代表
社会保険労務士 土井 美由紀 氏
・・・・・・・・・・・・・・・・
千葉県社会保険労務士会所属。社会保険労務士のほか、司法書士・行政書士・土地家屋調査士・弁護士・税理士等の士業法人・介護事業を総合的に対応する「最首総合事務所グループ」において、主に労働社会保険手続業務や労務管理の相談指導業務、年金相談業務などを行っている。
マイナビバイト掲載のご依頼や採用に関するお悩み、お気軽にご連絡ください!
「マイナビバイトの掲載料金が知りたい」「掲載の流れを知りたい」とお考えの採用担当者様は、ぜひ以下よりお問い合わせください。
マイナビバイトでは、求人掲載をお考えの方だけでなく、アルバイト・パート採用に関するお悩みをお持ちの方からのご相談も歓迎しております。私たちは、応募から採用・定着までをしっかり伴走し、貴社の課題解決に寄り添います。
マイナビバイトに問い合わせる(無料)
電話番号:0120-887-515(受付時間 9:30~18:00)
さらに、料金表・サービスの概要・掲載プラン・機能紹介などを詳しくまとめたサービス資料もご用意しています。
「まずは資料を見てみたい」という方は、下記リンクから無料でダウンロードいただけます。
マイナビバイトは、貴社の採用活動を全力でサポートいたします。ぜひこの機会にお問い合わせください。