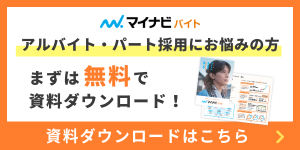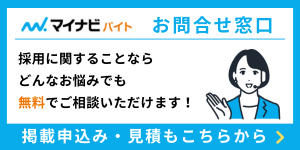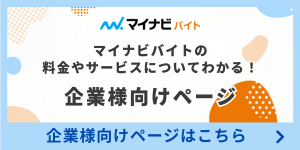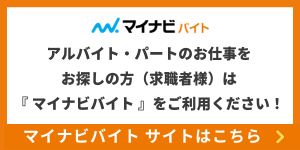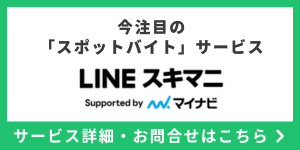新型コロナウイルス流行の影響が長引き、アルバイト・パートで働く人の中でも、職を失う方が出てきました。
アルバイトやパートは期間の定めがある「有期契約雇用者」ですが、だからといって
「契約を更新しなければ、契約期間終了後に退職してもらうことができる」
と考えてはいけません。
雇い止めが違法になるケースについて知っておきましょう。
見え始めたアルバイト、パート雇用状況の悪化
総務省4月の労働力調査によると、完全失業者数は上昇しています*1。
アルバイト、パートの就業者は減少しており、コロナウイルスの影響と考えられます。
そして、雇い止めにあった人たちの様子も報じられています。
イギリスのメディアが東京都庁前で取材したニュースでは、「ある日突然、職を失った」と話す人もいました。
ボランティアが食事を配る場所に長い列ができ、その中に多くの若者の姿があるという東京都庁前の様子も、このイギリスのニュースでは映し出されています。
実際、解雇や雇い止めにあった人の数は増え続けていて、厚生労働省の調査では、6月9日時点で2万人以上にのぼっています。
今後も増えると考えられます。
しかし、アルバイトやパートの雇い止めに関しては、労働者保護の観点から法律上の規定があります。
契約期間が終わったからそのまま退職させていいというものではありません。
「雇い止め」に関する規定
雇用契約の更新をしないことが違法にあたるかどうかは、それまでの契約状況や業務内容などによって異なります。
労働契約の内容は全ての前提
雇い止めによるトラブル防止のために、厚生労働省は労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)について基準を定めています。
労働基準法、労働契約法に基づいたものです。
そもそも、最初に労働契約を結んだ時、以下の項目を労働者に明示しておかなければなりません。
a 労働契約の期間
b 有期労働契約の更新の基準
c 就業場所・従事すべき業務
d 始業・就業時間、所定労働時間超えの労働の有無、休憩時間、休日、休暇、2交代制等に関する事項
e 賃金の決定・計算・支払い方法、賃金の締切・支払時期、昇給に関する事項
f 退職(解雇を含む)に関する事項
g その他(各種手当など)
特にb「有期労働契約の更新の基準」とf「退職に関する事項(解雇を含む)」が問題になるケースが相次いでいます。
そもそも労働契約を更新するのかどうかについて
・自動的に更新
・更新することもある
・更新はしない
など、最初に決めているはずです。
しかし「更新することもある」というのは曖昧なところがあり、そのためにbの「契約の更新の基準」を明示しておかなければなりません。
厚生労働省が「契約更新の基準」の例として示しているのは下のような項目です。
・契約満了時の業務量により判断する
・労働者の勤務成績、態度により判断する
・労働者の能力により判断する
・会社の経営状況により判断する
・従事している業務の進捗状況により判断する 等
なお、どんな判断であれ雇い止めをした場合には、その理由について証明書を出すように労働者から求められた場合は、会社は出さなければなりません。
その内容があまりに一方的なものであった場合、訴訟になる可能性もあるので注意が必要です。
そして今回多いのは「会社の経営状況」でしょう。
しかし、何をもって「経営状況の悪化」とするかは、雇用主が一方的に判断してはならないという決まりがあります。
事前に「売上がいくら未満になったら」という取り決めをしているような会社はほとんどないでしょう。そして、ここが問題になる点でもあります。この後詳しく説明します。
予告すれば良いわけではない
また、アルバイト・パートの雇い止めに関して、
・有期労働契約が3回以上更新されている
・1 年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新され、 最初に労働契約を締結して
から継続して通算 1 年を超える場合
・1 年を超える契約期間の労働契約を締結している場合
以上のケースでは、契約更新をしないことに関して30日前までに予告する義務があります。
ここで、予告をしてその月の分の給料を払えば良い、という誤解があるようですが、必ずしもそうではありません。
あくまで「やむを得ない」場合のことであり、「やむを得ない」というのはそう簡単な条件ではないからです。
期間満了でも雇い止めが「不当な解雇」となる
「やむを得ない」というのはどういうことなのか。
労働契約法の定めで、雇い止めが認められる範囲は限られています。
労働契約法による雇い止めの制限
労働契約法19条では、労働契約の更新を拒否できない場合について定められています。下のようなものです。
1)これまでの契約更新のされかたから、期間の定めのない労働者と業務内容が実質同じになっている場合
2)そうでなくても、契約更新回数などに関係なく、有期契約労働者が、今後の契約更新を期待できる「合理的な理由がある」場合
どちらかに当てはまる場合は、社会通念に照らして認められるような理由がなければ更新を拒否してはいけない、という内容です。
注意すべきは、これまで何回契約を更新したから、あるいはどんな仕事だから、ということが具体的には条文化されていないところです。
期間の定めのない正社員などの労働者と業務内容が実質同じ、というのは比較的わかりやすいのですが、問題は「合理的な理由」というところです。
過去の裁判では「業務内容が恒常的であり更新手続きが形式的」であったり、「雇用継続を期待させるような会社側の普段の言動が認められる」ことが、雇い止めを認められない理由になっています*2。
このような場合、正社員の整理解雇と同じくらいの理由を必要とされます。
なお、このように回数や期間などについて明確な数字がないのは、この条文はもともと、過去に相次いだ裁判の中で、最高裁が示した判断をのちに条文の中に取り入れたから(法理の条文化)、という経緯があります。
そして「社会通念に照らして」というのは表現としては曖昧ですが事案ごとに法廷で判断されるため、安易に雇い止めをするとどのような結果を招くかわからないリスクを抱えてしまいます。
「整理解雇の4条件」
それでも、どう考えても経済的に厳しいとなった場合、これは正社員の解雇と同様の要件が必要です。
「整理解雇の4条件」と呼ばれるものです。
1)人員削減の必要性
人員削減措置の実施が不況、経営不振などによる企業経営上の十分な必要性に基づいていること2)解雇回避の努力
配置転換、希望退職者の募集など他の手段によって解雇回避のために努力したこと3)人選の合理性
整理解雇の対象者を決める基準が客観的、合理的で、その運用も公正であること4)解雇手続の妥当性
労働組合または労働者に対して、解雇の必要性とその時期、規模・方法について納得を得るために説明を行うこと<引用:「労働契約の終了のルール」厚生労働省>
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/keiyakushuryo_rule.html
ここでも「不況、経営不振」は、事前の労働契約にその基準が明示されていない場合、裁判所の判断となります。
他の要件についても、「アルバイトだから真っ先にやめさせても良い」というものではありません。
リーマン・ショックと「派遣切り」裁判
不況といえば、近いところではリーマン・ショックが挙げられます。
多くの企業、特に工場勤務者の「派遣切り」が相次ぎ、社会問題にもなりました。
この時、多くのメーカーで労働者が訴訟を起こしました。
「正社員と実質同じ仕事をしている」という理由で地位確認を求めたものです。
そして、労働者側の主張が認められるケースも相次ぎました。
それまでの労働形態や実績に基づいて判断されたものです。
最終的には和解に至っているケースが多いようですが、前例として示されたことに留意をしなければなりません。
また、東日本大震災においても、震災を理由とした雇い止めには制約がありました。
基本的には上記の労働契約法第19条の遵守が先にあります。
厚生労働省は、このような見解を示しています。
・今回の震災で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受けたために事業の全部又は大部分の継続が不可能となった場合は、原則として、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」に当たるものと考えられます。
・事業場の施設や設備が直接的な被害を受けていない場合には、事業の全部又は大部分の継続が不可能となったときであっても、原則として「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」による解雇に当たりません。
<引用:「震災に伴う解雇について」>
https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/koyou_roudou/2r98520000017fj4.html
今回は、新型コロナウイルスという未知の感染症が、未曾有とも言える被害をもたらしていますが、厚生労働省から経済団体に対して、やはり労働契約法19条に基づく要請がなされています*3。
かつ、今回も法律家や関係団体が相談窓口を設置していることから、この流れが加速すると行政の介入や集団訴訟、あるいは労働組合立ち上げの上での訴訟は十分あり得ることでしょう。
リーマン・ショックと「派遣切り」裁判
「事業主の判断」に委ねられる今回の対応
今回は未知の感染症という初めての事態で、整理解雇の4条件「解雇の必要性」についてまだ主な判例はありません。
ただ、休業補償に関する厚生労働省の見解を見ると、「事業主が適宜判断」という色合いが非常に濃いように受け取れます。
あくまで「自粛」であり企業の判断による、という見解と考えられます。
よって解雇についても、どこまで不可抗力だったかどうかについては結果的に裁判所の判断によるものの、休業補償と同様の見解が示される可能性も排除できません。
労働契約に関する法律上もっとも大事にされているのは、「労使双方の合意」です。
今のうちから何らかの方法で労使合意を形成することも選択肢の一つになるでしょう。
もちろんその場合は契約内容を詳細に決める必要があります。
新型コロナウイルスによる人員整理に関しては先般、ある企業が社員を一斉解雇しようとした事例が報じられました。
経営側の主張としては
「給料を払えなくなるよりも、失業手当を受けられるようにした方が社員のため」
というものでしたが、労働者との合意形成がなかったために大問題になりました。
現下の状況は、労働者を最大限守る方向にありますから注意が必要です。
*1 「労働力調査 2020年(令和2年)4月分」総務省
https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/pdf/gaiyou.pdf p1
*2 「労働契約法改正のあらまし」厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/pamphlet.pdf p16
*3 「新型コロナウイルス感染症に係る有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々並びに新卒の内定者等の雇用維持等に対する配慮に関する要請書」厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/000614053.pdf
<清水 沙矢香>
2002年京都大学理学部卒業後、TBS報道記者として勤務。
社会部記者として事件・事故、科学・教育行政その後、経済部記者として主に世界情勢とマーケットの関係を研究。欧米、アジアなどでの取材にもあたる。
ライターに転向して以降は、各種統計の分析や各種ヒアリングを通じて、多岐に渡る分野を横断的に見渡す視点からの社会調査を行っている。
Twitter:@M6Sayaka
マイナビバイト掲載のご依頼や採用に関するお悩み、お気軽にご連絡ください!
「マイナビバイトの掲載料金が知りたい」「掲載の流れを知りたい」とお考えの採用担当者様は、ぜひ以下よりお問い合わせください。
マイナビバイトでは、求人掲載をお考えの方だけでなく、アルバイト・パート採用に関するお悩みをお持ちの方からのご相談も歓迎しております。私たちは、応募から採用・定着までをしっかり伴走し、貴社の課題解決に寄り添います。
マイナビバイトに問い合わせる(無料)
電話番号:0120-887-515(受付時間 9:30~18:00)
さらに、料金表・サービスの概要・掲載プラン・機能紹介などを詳しくまとめたサービス資料もご用意しています。
「まずは資料を見てみたい」という方は、下記リンクから無料でダウンロードいただけます。
マイナビバイトは、貴社の採用活動を全力でサポートいたします。ぜひこの機会にお問い合わせください。