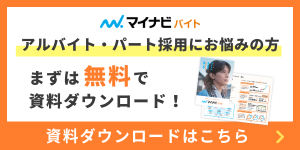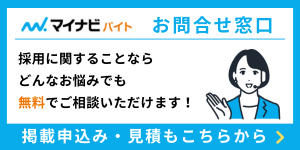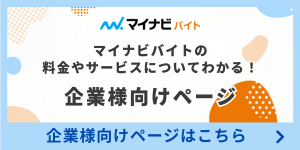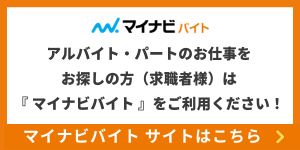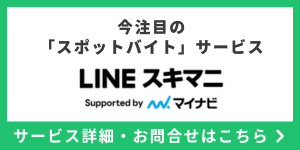新型コロナウイルスの影響が長引き、多くの企業が事業の縮小を余儀なくされています。
しかし一方で、今だからこそアルバイトや社員の採用を増やす企業も存在しています。
この状況の中で採用を増やそうという企業は、何を目的にどのような活動をしているのでしょうか。
目次
「収入減で退学も」検討する学生
マイナビの調査によると、アルバイトをしている大学生のうち、アルバイトの目的は「貯金のため(58.5%)」という学生がもっとも多くなりました。
次いで多かった回答が「生活費のため(48.9%)」で、おおよそ半数にのぼります*1。
「交際費を稼ぐため」というのなら生活を変えることである程度しのいではいけるでしょうが、生活費のためとなるとそうは行きません。
2020年4月末には、アルバイト収入が減ったことで退学を考える学生が一定数いるとも報じられています。
業種によっては親の収入も同時に減少していることも考えられます。そうなると経済的に頼る相手がいなくなり、より深刻な事態になっていることも考えられます。
コロナ・ショック下での採用強化
一方、この環境下でアルバイトや社員の積極採用に踏み切る企業も出ています。
目的はいくつかあるようです。
■「コロナ後」を見据えたアルバイトの大量採用
あるフードデリバリーチェーンでは、コロナウイルスによって経済や雇用への影響が明らかになってきた4月から、アルバイト採用が活発になっています。
このチェーンではもともと長期戦略として店舗数拡大を掲げています。
しかし現在の状況を逆手にとって人手を確保し、かつ雇用の受け皿になるという社会的役割も同時に果たす結果になっています。
もちろん、このように企業の事情とコロナウイルスの影響が噛み合うことの方が少ないかもしれません。しかし「長期の計画」と「時期を逃さない機動力」があったことが大きなポイントです。
また先日筆者は、何人かの企業経営者と話す機会がありました。
逆境の中、意欲的な経営者たちは様々な工夫をしています。
これは正社員についての話ではありますが、あるIT企業では、
「今だからこそ、普段出会えないような優秀な人材が世に出ている」
と考えて採用活動に集中しているということです。
営業活動が自由にできない環境下で「この2年でやりたいこと」を即座に設定し、そのために必要な人材を絞り込んで募集・採用することが可能になっています。
社内の人材構成の見直しや、本当に欲しい人材の絞り込みという課題に腰を据えて取り組む時期だと発想を切り替えてはいかがでしょうか。
それに伴い、事業戦略や採用戦略の練り直しに充てるということも、非常に有効と言えそうです。
「コロナ後」社会はどう変化しているか
現在のコロナ禍が去った後、世の中や働き方はどのように変化しているかということも話題になりつつあります。
通勤という概念がなくなるのではないか、都市への集中がなくなるのではないか、消費者の生活やお金の使い方がコンパクトになるのではないか、と様々な意見が出ています。
その中で、ひとつ参考にしたい動きがあります。
■新しい雇用の形「従業員シェア」
海外から始まったのが、産業を超えた従業員シェアです。
例えば、アメリカの大手スーパーマーケットチェーンは3月末に、ホテルや外食の従業員を含む2万人を雇い入れると発表しています。
ホテルや外食産業が大打撃を受けている一方で、生活必需品を販売するスーパーマーケットは人手不足になっています。
店頭だけでなく工場、流通センターにも人手を必要とするため、専門的な仕事ではない所で多くの雇用を生み出すことが可能です。
現在「仕事が激減している業種」と「人手不足になっている業種」があり、仕事の量が極度に偏っています。
この状況で必要な考え方は、まずは補い合うこと。
そして経済が正常化すれば。人手の需要も正常化することまで織り込んでいる動きなのです。
同様にイギリスでは、大手ホテルチェーンが通信販売企業の求人を社員に紹介し、自社との雇用契約を切らないまま他業種に仕事を求める手伝いをしています。
いつでも戻ってこられる措置です。
中国、ドイツでも通信販売企業が飲食店店員などを受け入れる動きがあります。
日本でもこれまでとは異なる働き方が広がるかもしれません。
コロナ前では考えられなかった従業員シェアという形は
「従業員の生活を第一に考えた結果生まれた」
というのが最大のポイントです。
自社の人手確保だけではない新しい雇用の形は、企業同士の横の関係として今後の災害対応時の、新しい考え方となるかもしれません。
こうした柔軟な取り組みは企業イメージの向上にも繋がります。
「従業員の生活を第一に考える」
このようなスタンスを守ることは、長期的に見て会社のプラスになりそうです。
仕事がないなら「作る」というアプローチ
また、先日筆者が話す機会をもらったある企業では「社内での事務作業をするアルバイト」の求人広告を出しています。
パソコンの基本的な操作ができれば良いという条件で、業務内容は社内の資料整理や伝票データの打ち込みです。
事務専門の職員がいなかったために溜め込みがちになっていた仕事を、営業活動がしづらい今のうちに人を雇い、一気に済ませようというものです。
良い人材であればそのまま事務職として働き続けてもらうことも考えていると言います。
また、イベント会社の話もありました。最も早い段階から影響を受けている業界です。
この社長は、まず「当面の現金」を可能な限りかき集め、会社の形を維持することから始めています。
そして、今後は動画配信などWebでのビジネス方法を模索する時期に充て、動画サンプルを作成させるなどの業務に人員を振り分けています。
もともと、大きな事務所を必要としない「固定費のコンパクトさ」もこの方法を有効にしていると考えられます。
コロナ禍が示したのは、長期的な視点がいかに必要かということです。
従業員シェアも長期的に見れば「広い意味での人手確保」です。
前例のない所に前例を作るという姿勢がなければ、次の有事には対応できないでしょう。
アルバイトと共に会社を創るという発想へ
休校が長引き、働き場所を失い、また就職活動のスケジュールが不透明になったり、中には内定を取り消された学生もいる厳しい環境です。
逆に多忙を極める小売店などでは、買い物客の問題行動に精神的なストレスを抱えています。
このような時こそ、アルバイトとして働いてくれる従業員への心のケアが必要です。
厳しい経験を共にすることは、会社にとっても従業員にとっても今後の糧になるでしょう。
*1 「マイナビ 2020年大学生のアルバイト実態調査」
https://www.mynavi.jp/news/2020/04/post_23134.html
<清水 沙矢香>
2002年京都大学理学部卒業後、TBS報道記者として勤務。
社会部記者として事件・事故、科学・教育行政その後、経済部記者として主に世界情勢とマーケットの関係を研究。欧米、アジアなどでの取材にもあたる。
ライターに転向して以降は、各種統計の分析や各種ヒアリングを通じて、多岐に渡る分野を横断的に見渡す視点からの社会調査を行っている。
Twitter:@M6Sayaka
この記事を読んだ人におすすめ!
マイナビバイト掲載のご依頼や採用に関するお悩み、お気軽にご連絡ください!
「マイナビバイトの掲載料金が知りたい」「掲載の流れを知りたい」とお考えの採用担当者様は、ぜひ以下よりお問い合わせください。
マイナビバイトでは、求人掲載をお考えの方だけでなく、アルバイト・パート採用に関するお悩みをお持ちの方からのご相談も歓迎しております。私たちは、応募から採用・定着までをしっかり伴走し、貴社の課題解決に寄り添います。
マイナビバイトに問い合わせる(無料)
電話番号:0120-887-515(受付時間 9:30~18:00)
さらに、料金表・サービスの概要・掲載プラン・機能紹介などを詳しくまとめたサービス資料もご用意しています。
「まずは資料を見てみたい」という方は、下記リンクから無料でダウンロードいただけます。
マイナビバイトは、貴社の採用活動を全力でサポートいたします。ぜひこの機会にお問い合わせください。